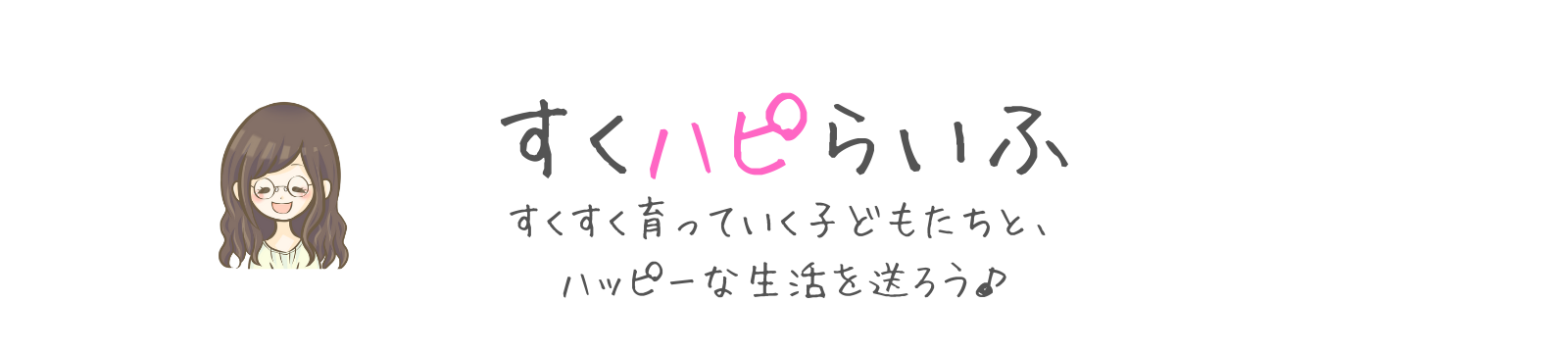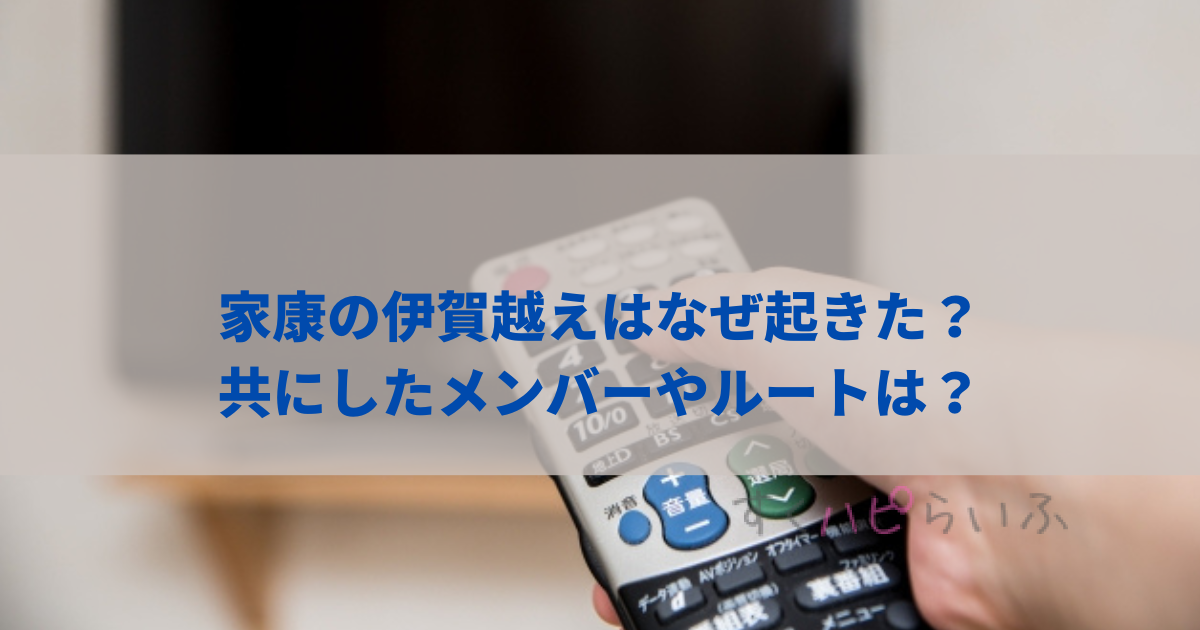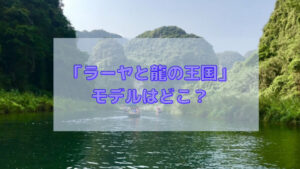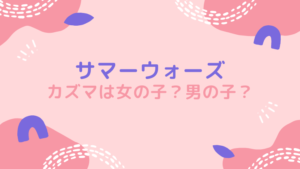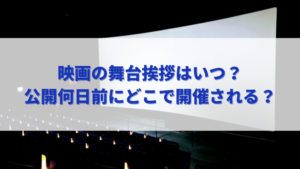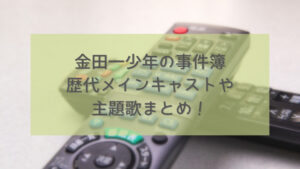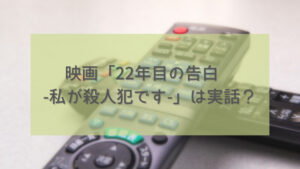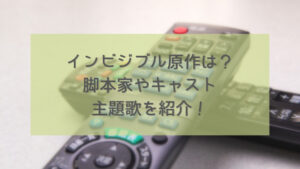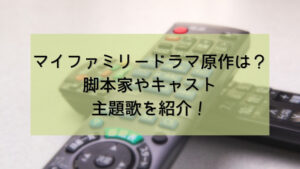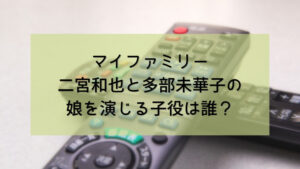家康の伊賀越えはなぜ起きたのでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」、とても話題になっていますね!
新しい家康像が、主演の松本潤さんや、家臣団の皆さんの熱演で大きな話題となっています。
そんな「どうする家康」で注目されているのが、家康の三大危機と言われている出来事です。
三大危機とは、
- 三河一向一揆
- 三方ヶ原の戦い
- 伊賀越え
この3つの出来事です。
どれも家康にとっては大きな命の危機でしたが、最後の「伊賀越え」はあの本能寺の変にまつわることもあり、大きく注目されています。
そこでこの記事では、家康の伊賀越えについて詳しく紹介していきます。
伊賀越えはなぜ起きたのか、そして共にしたメンバーやルートはどのようなものなのか、より深く掘り下げてみました。
これを読むと、ドラマ「どうする家康」をさらに楽しめるかもしれません。
歴史の面白さ、ぜひ感じてみてくださいね。
家康の伊賀越えはなぜ起きた?
家康の伊賀越えはなぜ起きたのでしょうか?
原因や背景に迫ってみました。
伊賀越えの原因は、あの「本能寺の変」です。
1582年、東国を平定した信長は、天下統一のため西の大名・毛利氏を討伐するため、京都に入ります。
同年5月、家康は安土城を訪れ、次の月である6月には堺見物をしていました。
そんな時、京都の本能寺に滞在していた信長が、家臣である明智光秀の襲撃を受け、自害してしまいます。
いわゆる「本能寺の変」ですね。
この事件は、家康に大きな精神的ショックを与えます。
松平家にゆかりのある「知恩院」に籠った家康は、そこで自害しようとします。しかし家臣の1人である本多忠勝(どうする家康では、山田裕貴さんが演じられています)に説得され、故郷の岡崎に戻ることを決意します。
ここから、命懸けの旅である「伊賀越え」が始まるのです。
信長という後ろ盾を失った家康は、この時、とても微妙な立場に置かれていました。
信長が倒されたことで、戦国のパワーバランスは崩れ、状況は混沌としています。
落武者狩りにも執拗に狙われる中、家康は、生涯の三大危機のひとつである伊賀越えに挑むことになるのです。
伊賀越えを共にしたメンバーは?
家康が伊賀越えを共にしたメンバーには、どのような人たちがいるのでしょうか?
伊賀越えのメンバーは、総勢34名いたと言われています。
このわずかな手勢で、執拗に襲いかかる一揆勢を打ち倒しながら伊賀越えを果たさなければならなかったのです。
注目すべきは、この「伊賀越え」のメンバーの中に、あの徳川四天王がいたということです。
徳川四天王とは、家康の腹心中の腹心である4人の家臣のことを指します。
徳川四天王とは、
- 酒井忠次
- 本田忠勝
- 榊原康政
- 井伊直政
この4名の家臣のことです。「どうする家康」のドラマでも、毎回活躍しています。
「伊賀越え」は、家康にとって命懸けの旅でした。
これを共に乗り越えたことで、のちに四天王となる家臣たちとの絆も深まったことでしょう。
その他にも、家康の「伊賀越え」には多くの人々が関わっていました。
中でも代表的なのは、商人である「茶屋四郎次郎」と「角屋七郎次郎」、そしてあの「服部半蔵」です。
ドラマ「どうする家康」でも活躍している彼らですが、服部半蔵は伊賀越えの際、家康たちの道案内を務めたと言われています。
ただ、不思議なことに、徳川の歴史書の中に服部半蔵の名前は出てこないんです。
しかし服部家はその後も家康に仕え、江戸幕府が開かれた後は、江戸城周辺の警備にあたったと言われています。
歴史書に名前がないのに、とても有名な忍びである服部半蔵らしいエピソードですよね。
商人「茶屋四郎次郎」は、家康と年齢が近く、以前から家康と親交があったと言われています。
「本能寺の変」が起こったことを、いち早く家康に伝えたのも、この茶屋四郎次郎です。
「どうする家康」でも、中村勘九郎さんがとても印象的な演技をされています。
一度見たら忘れられないインパクトでしたが、この茶屋四郎次郎、商人としての経済力を活かし、家康の「伊賀越え」をサポートします。
逃走経路や物資の確保、さらに地元の住民との交渉役まで担い、家康を力の限りサポートしたんです。
同じく商人である「角谷七郎次郎」も、商人としての力を最大限に活かし、家康をサポートしました。
角屋七郎次郎は、廻船問屋を営んでいました。持ち前のノウハウを生かし、「伊賀越え」では、伊勢国から三河国までの船を用意し、家康が海路で脱出する手助けをしています。
茶屋四郎次郎も、角屋七郎次郎も、この時の活躍を家康に高く評価され、のちに大きな富を築いています。
彼らは商人として、家康に将来を賭けたのかもしれません。
そしてその賭けは、大成功を収めたんですね!
伊賀越えのルートとは?
家康の「伊賀越え」のルートは、どのようなものだったのでしょうか?
伊賀越えは、なんと全長200キロにも及ぶと言われています。
そのルートには諸説ありますが、ここではその一説を紹介します。
信長の勧めで堺見物をしていた家康は、そこで本能寺の変が起きたことを知ります。
京都や堺を訪れる前、警備の手薄さを明智光秀に知られていた家康。さらに信長という後ろ盾を突然失ったことにより、家康は自分が危うい立場に置かれたことに気が付きます。
一度は自害を考えますが、本田忠勝の説得により、わずか34名の家臣と共に、故郷の岡崎に戻ることを決意します。
まず家康は、堺から陸路で柏原へ向かいます。その後、船で河内湖を渡り、飯盛山の麓に上陸します。
その時、かつて武田の家臣であった穴山信君も家康に同行していました。
その後、住吉平田神社宮司である三牧家に立ち寄った家康は、里の人々や農民たちの案内で、田辺の飯の丘にたどり着きます。
この時、別行動をとっていた穴山信君は、この地で殺されたと伝えられています。
これはショッキングな事実ですよね。
ここから家康は、地元の侍の案内で宇治田原へ向かいます。宇治田原の入り口には、信長の命令で建てられた山口城がありました。
山口城の城主は家康がこちらに向かっていることを知り、配下を迎えに行かせます。
この城で食事をとり、一息ついたあと、家康は再び岡崎に向けて出発します。
信楽街道を抜け、裏城峠を越えて多羅尾氏の小川城に入り、そこで仮眠をとります。小川城の城主は、山口城の城主の息子でした。
翌日再び出発した家康は、伊賀、関、亀山、白子港、海路三河大浜をへて、岡崎へと無事に帰還したのです。
道中、穴山信君の死というショッキングな出来事もありつつ、命からがら岡崎へ辿り着いた家康。
その道のりは、とても言葉にできないような激しさだったと言われています。
当時、落武者を狙った一揆勢が横行していました。彼らは戦に敗れた武士を殺し、身ぐるみを剥いで生活の糧にしていたのです。
後ろ盾の信長を失ったことで、「もう終わった人」と思われていた家康も、執拗に一揆勢に狙われます。
一説では、わずか34名の手勢で、200名以上の一揆勢を切り捨てて進んできたと言われています。
しかしこの「伊賀越え」を共に乗り越えたことで、家康と家臣たちとの絆は深まります。
さらに家康は、伊賀越えに協力した農民や商人たちへの恩を忘れることなく、彼らに褒賞を与えたと言われています。
「伊賀越え」で作られた絆が、のちの天下統一へと繋がっていったんですね。
まとめ:家康の伊賀越えはなぜ起きた?共にしたメンバーやルートについても紹介
家康の「伊賀越え」はなぜ起きたのか、そして同行者やルートについて紹介しました。
家康の伊賀越えは、三河一向一揆、三方原の戦いと並ぶ、家康の生涯三代危機のひとつです。
あの「本能寺の変」に原因があるということで、とてもドラマチックな側面もありますよね。
命懸けの壮絶な旅でしたが、ここで同行した家臣たちや、協力した商人や農民、地元の人たちへの恩を、家康は忘れることはありませんでした。
その後の彼らへの待遇に、家康の天下人としての資質を見ることができるように思います。
この後も、家康には多くの苦難が待ち受けています。
それらを乗り越える基盤が、この「伊賀越え」で築かれたのかもしれません。
知れば知るほどドラマチックな「伊賀越え」を通し、歴史の妙を感じてみてくださいね。